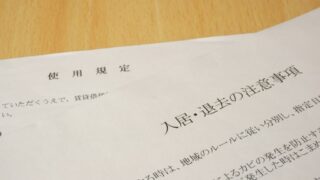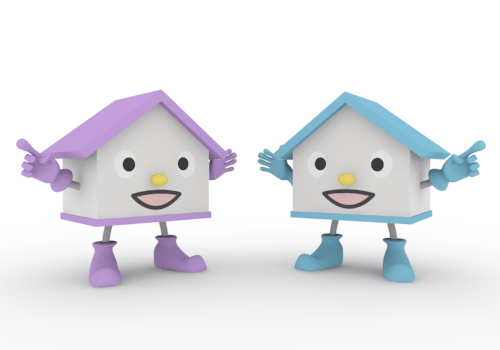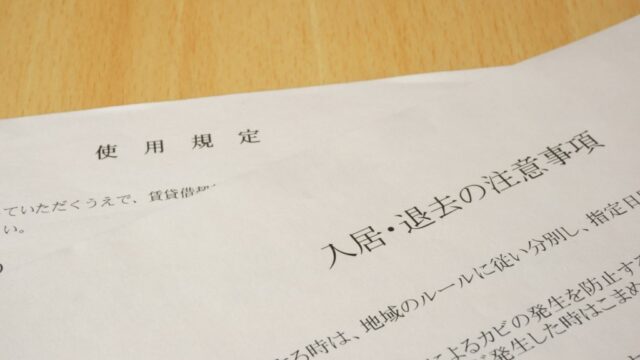賃貸マンションやアパートに住み続けていると、1年や2年に一度やってくる「契約更新」。
その際に「更新のお知らせ」といった書類とともに請求される「更新料」について、「これって一体何のお金?」「必ず払わなければいけないの?」と疑問に思ったことはありませんか?
特に初めて契約更新を迎える方にとっては、家賃1ヶ月分にもなることがある更新料は大きな負担に感じられるかもしれません。しかし、更新料の意味や相場、そして交渉の可能性について正しく知っておけば、漠然とした不安を解消し、納得して手続きを進めることができます。
この記事では、不動産のプロの視点から、賃貸契約の更新料の基本知識、地域による相場の違い、そして更新時に家賃や更新料を交渉するための具体的な方法まで、詳しく解説していきます。
そもそも「更新料」とは?支払う義務はあるの?
契約更新のタイミングで当たり前のように請求される更新料ですが、その目的や法的な位置づけを正しく理解している方は少ないかもしれません。
まずは、更新料の基本的な意味合いと、支払い義務の有無について確認していきましょう。高額な費用だからこそ、その根拠をしっかり把握しておくことが重要です。
更新料の目的と法的根拠
更新料とは、賃貸借契約を更新する際に、借主(入居者)から貸主(大家さん)に対して支払われる一時金のことです。
これは、長年にわたり住み続けてもらうことへの謝礼や、契約を継続するための対価といった意味合いを持つ、古くからの商慣習の一つとされています。
法的に明確な定めがあるわけではありませんが、過去の判例では「賃料の補充や前払い、契約を継続するための対価などの複合的な性質を持つもの」とされており、賃貸借契約書に更新料に関する特約が明記されている場合、その支払い義務は有効であると判断されています。
つまり、契約時に内容を合意したうえで署名・捺印している以上、支払う義務が生じるのです。
契約書に記載があれば支払い義務が発生する
更新料の支払い義務の有無を判断する最も重要なポイントは、「賃貸借契約書」に記載があるかどうかです。
契約を結ぶ際に、更新料の金額や支払い時期について具体的な記載があり、それに対して合意していれば、原則として支払いを拒否することはできません。
もし契約更新の通知が来て更新料の支払いを求められたら、まずは手元にある賃貸借契約書を確認しましょう。
「契約を更新する場合、借主は貸主に対し、更新料として新賃料の〇ヶ月分を支払うものとする」といった条文があるはずです。
逆に、契約書に更新料に関する記載が一切なければ、支払う義務はありません。
更新料と「更新事務手数料」の違い
更新料と混同されやすい費用に「更新事務手数料」があります。この二つは性質が全く異なるので注意が必要です。
- 更新料: 貸主(大家さん)に支払うお金。
- 更新事務手数料: 契約更新の手続きを行う不動産管理会社に支払うお金。
更新事務手数料は、新しい契約書の作成や火災保険の更新手続きなど、更新業務にかかる手間賃として発生します。相場は1万円〜3万円程度が一般的です。
契約によっては、更新料と更新事務手数料の両方が必要になるケースもありますので、請求内容の内訳をしっかり確認しましょう。
【地域別】賃貸の更新料、相場はいくら?
更新料の金額は全国一律ではなく、地域によって大きく異なる傾向があります。これは、それぞれの地域の不動産取引における慣習の違いが影響しているためです。
お住まいの地域の相場を知ることで、請求されている金額が妥当かどうかを判断する一つの目安になります。
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の相場
首都圏では、更新料は「家賃の1ヶ月分」というのが最も一般的な相場です。
契約期間は2年ごととなっている物件が多く、2年ごとに家賃1ヶ月分の更新料が発生するケースが主流です。人気エリアや築浅の物件などでは、需要の高さからこの相場が定着しています。
関西(大阪・京都・兵庫)の相場
一方、関西地方、特に大阪では更新料の慣習がほとんどありません。その代わり、「保証金」や「敷引(しきびき)」といった独自の契約文化が存在します。
ただし、近年は全国展開する不動産会社の影響や、貸主側の意向により、関西でも更新料を設定する物件が少しずつ増えてきています。京都では一部のエリアで更新料が必要な場合があります。
その他の地域の傾向
その他の地域、例えば東海地方や九州地方などでは、更新料がかからない物件も多いですが、地域や物件によって様々です。
家賃の0.5ヶ月分であったり、数万円の定額であったりと、設定は多岐にわたります。全国的に見ると、更新料は首都圏を中心とした慣習であり、地方では必須ではないケースも多いと言えるでしょう。
更新料がかからない物件もある?
更新料の支払いを避けたい場合は、最初から更新料がかからない物件を選ぶという選択肢もあります。代表的なのは以下の2つです。
-
UR賃貸住宅: 独立行政法人都市再生機構(UR)が管理する物件は、礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要な「4つのナシ」が特徴です。初期費用や更新時の負担を抑えたい方には大きなメリットです。
-
公営住宅: 都営住宅や県営住宅などの公営住宅も更新料はかかりません。ただし、入居には所得制限などの条件があります。
また、民間の賃貸物件でも、空室対策として「更新料なし」をアピールしている物件もあります。物件探しの際に、この条件を加えて探してみるのも良いでしょう。
更新料や家賃は交渉できる?プロが教える交渉術
「契約書に書いてあるから、交渉なんて無理だろう」と諦めていませんか?実は、更新料や次年度からの家賃は、交渉できる可能性があります。
もちろん必ず成功するわけではありませんが、いくつかのポイントを押さえて賢く交渉することで、支出を抑えられるかもしれません。
交渉のベストなタイミングはいつ?
交渉を切り出すタイミングは非常に重要です。最も効果的なのは、契約更新の通知が届いてから、更新手続きの回答をするまでの間です。
一般的に、契約期間が満了する2〜3ヶ月前に大家さんや管理会社から「契約更新のご案内」といった書類が届きます。この通知を受け取ってから、1〜2週間以内に連絡するのがベストタイミングです。
期間満了ギリギリになってしまうと、大家さん側も手続きを進めてしまっており、交渉に応じてもらいにくくなります。余裕を持ったスケジュールで行動することがおすすめです。
交渉を有利に進めるための準備(情報収集)
交渉は、ただ「安くしてください」とお願いするだけでは成功しません。
大家さんに「この入居者なら、条件を飲んででも長く住み続けてほしい」と思わせるような、客観的な根拠を示すことが重要です。
近隣の類似物件の家賃相場を調べる
まずは、自分の住んでいる物件と同じような条件(エリア、間取り、築年数、駅からの距離など)の物件が、現在いくらで募集されているかを調べましょう。
不動産情報サイトなどで簡単に検索できます。もし、近隣の類似物件の家賃が、自分の部屋の現在の家賃よりも安い場合、それは強力な交渉材料になります。
調査例:
- 「同じマンションの別の部屋が、今の家賃より5,000円安く募集中です。」
- 「近隣の同じような築年数・広さの物件は、〇〇円が相場のようです。」
設備の不具合や改善してほしい点をまとめる
「エアコンの効きが悪い」「給湯器の調子が良くない」など、設備に関する不具合がある場合も交渉の材料になります。
「この設備を修理・交換してくれるなら、提示された条件で更新します」といった形で、交換条件として交渉するのも有効な手段です。普段から気になっている点があれば、メモしておきましょう。
【例文あり】交渉時の伝え方とマナー
交渉の際は、伝え方が非常に重要です。高圧的な態度や、一方的な要求は絶対に避けましょう。
あくまで「お願い」「相談」という低い姿勢で、丁寧な言葉遣いを心がけることが、相手の心証を良くし、交渉をスムーズに進めるコツです。
交渉時のポイント
-
感謝を伝える: 「いつもお世話になっております」「長く住まわせていただきありがとうございます」など、まずは感謝の気持ちを伝えます。
-
長く住み続けたい意思を示す: 「今後も長く住み続けたいと考えているのですが…」と前置きすることで、大家さん側のメリットを伝えます。
-
客観的な根拠を示す: 「近隣の相場を調べたところ…」「実は設備の件でご相談がありまして…」と、準備した情報を具体的に伝えます。
-
相談ベースで話す: 「〇〇円にお値下げいただくことは可能でしょうか?」と、命令ではなく質問の形で伝えます。
電話での交渉例文
「お世話になっております。〇〇号室の〇〇です。先ほど契約更新の書類を拝見いたしました。
こちらの物件を大変気に入っており、今後も長く住み続けたいと考えているのですが、更新の条件について少しご相談させていただくことは可能でしょうか。
実は、近隣の同じような条件の物件の家賃相場を調べたところ、現在の家賃よりも少しお安いようでして…。
もし可能でしたら、来月からの家賃を〇〇円にお値下げいただくことは難しいでしょうか?」
交渉が成功しやすいケース・難しいケース
交渉が成功するかどうかは、いくつかの要因によって左右されます。
交渉が成功しやすいケース:
- 長期間、問題なく居住している(家賃滞納などがない優良な入居者)
- 近隣の家賃相場が明らかに下落している
- 同じマンション内に空室が多い
- 不動産の閑散期(4月〜8月頃)
交渉が難しいケース:
- 人気の高い物件で、空室が出てもすぐに次の入居者が見つかる
- 入居期間が短い
- 過去に家賃滞納などのトラブルがあった
- 不動産の繁忙期(1月〜3月頃)
賃貸契約の更新時に注意すべきポイント
最後に、更新料や家賃の交渉以外で、契約更新時に注意すべき大切なポイントをいくつかご紹介します。手続き漏れなどがないように、しっかり確認しておきましょう。
更新の意思は早めに伝える
更新するにせよ、退去するにせよ、その意思はできるだけ早く管理会社や大家さんに伝えましょう。多くの契約では「期間満了の1ヶ月前までに意思表示をすること」と定められています。
これを過ぎてしまうと、自動的に契約が更新されたとみなされたり、余計な費用が発生したりする可能性があるので注意が必要です。
火災保険の更新も忘れずに
賃貸契約とセットで加入していることが多い火災保険も、通常は同じタイミングで更新時期を迎えます。
これを忘れると、万が一火災や水漏れなどを起こしてしまった際に補償が受けられなくなってしまいます。更新手続きの案内に火災保険に関する記載がないか、必ず確認しましょう。
保証会社の契約更新について
保証会社を利用している場合、そちらの契約更新も必要になることがあります。
保証会社との契約も、賃貸借契約とは別個の契約です。更新料(保証委託料)が発生することが多いので、忘れないようにしましょう。
更新しない(退去する)場合の選択肢
交渉がうまくいかなかったり、より良い条件の物件を見つけたりして、更新せずに退去するという選択肢もあります。そ
の場合は、定められた期限までに「解約通知書」を提出する必要があります。
引越しには初期費用がかかりますが、更新料を支払う代わりに新しい環境で生活を始めるのも一つの手です。
更新料の金額と、引越しにかかる費用を天秤にかけて、どちらが自分にとってメリットが大きいかを冷静に判断しましょう。
まとめ
今回は、賃貸契約の「更新料」について、その基本から相場、交渉術までを詳しく解説しました。
- 更新料は契約書に記載があれば支払い義務がある
- 相場は地域によって異なり、首都圏では家賃1ヶ月分が主流
- UR賃貸など更新料がない物件もある
- 家賃や更新料は、タイミングと伝え方次第で交渉できる可能性がある
- 交渉の際は、客観的な根拠と丁寧な姿勢が重要
契約更新は、現在の住まいの住み心地や家賃が適正かを見直す良い機会です。
更新料や家賃について正しく理解し、時には交渉という選択肢も持ちながら、賢く手続きを進めていきましょう。この記事が、あなたの快適な賃貸ライフの一助となれば幸いです。