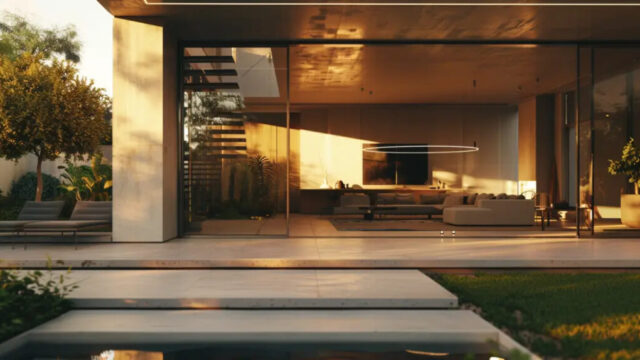働き方の多様化に伴い、自宅をオフィスとして活用する「SOHO」や、住居兼事務所のニーズが高まっています。
しかし、一般的な居住用賃貸物件では事業利用が認められていないケースが多く、物件探しに苦労している方も少なくありません。
また、運よく「SOHO可」「事務所利用可」の物件を見つけても、契約形態や利用条件など、事前に確認すべき点が多く、知識がないまま契約を進めると後々トラブルに発展する可能性もあります。
この記事では、これからSOHOや事務所として利用できる賃貸物件を探す方に向けて、物件探しの具体的なポイントから、契約前に必ず確認すべき注意点、契約形態による違いまで、分かりやすく解説します。
SOHO・事務所利用可物件とは?
SOHOや事務所として利用できる物件を探す前に、まずはそれぞれの言葉の意味や違いを正しく理解しておくことが重要です。
一般的な「在宅ワーク」とは異なる点も多く、大家さんや不動産会社に事業内容を説明する際にも、正確な知識が役立ちます。
ここでは、「SOHO」「事務所」「在宅ワーク」のそれぞれの特徴と違いについて解説します。
SOHOとは?
SOHO(ソーホー)とは、「Small Office Home Office」の頭文字をとった言葉で、小さなオフィスや自宅を仕事場とする働き方、またはその事業形態を指します。
明確な法的定義はありませんが、一般的にはパソコンなどの情報通信機器を活用して、個人または数名の少人数で事業を行うスタイルを指すことが多いです。
例えば、ライター、デザイナー、プログラマー、コンサルタントなど、主にデスクワークが中心で、来客が少ない職種がSOHOの代表例として挙げられます。
住居の一部を仕事場として利用するケースが多いため、「住居兼事務所」という形態になります。
事務所との違い
「事務所」は、SOHOよりも事業の拠点としての意味合いが強くなります。
SOHOが「住居がメインで、一部を仕事場として利用する」というニュアンスであるのに対し、「事務所」は「事業を行うための専用スペース」を指します。
そのため、「事務所利用可」の物件は、不特定多数の人の出入りがある程度想定されていたり、看板の設置が許可されていたりする場合があります。
ただし、住居用の建物の一室を事務所として貸し出している「マンションオフィス」のような形態も多く、事業内容によっては利用が制限されることもあるため、事前の確認は不可欠です。
在宅ワークとの違い
在宅ワークは、企業に雇用されている従業員が、会社のオフィスではなく自宅で業務を行う働き方を指します。あくまでも勤務場所が自宅であるだけで、個人事業主として事業を営むSOHOとは異なります。
賃貸物件の契約上、在宅ワークは「居住」の範囲内と見なされることがほとんどです。そのため、大家さんや管理会社の許可を得る必要は基本的にありません。
一方、SOHOや事務所利用は「事業」と見なされるため、契約前に必ず許可を得る必要があります。
この違いを理解しておかないと、契約違反になる可能性があるので注意しましょう。
SOHO・事務所利用可物件の探し方
SOHOや事務所として利用できる物件は、一般的な居住用物件に比べて数が少ないのが現状です。
しかし、探し方のコツさえ押さえれば、効率的に理想の物件を見つけることが可能です。ここでは、具体的な物件の探し方と、検索する際の注意点について解説します。
不動産ポータルサイトでの検索方法
最も手軽な探し方は、不動産ポータルサイトを活用する方法です。「SUUMO」や「LIFULL HOME’S」などの大手サイトには、「SOHO可」「事務所相談」といった条件で絞り込んで検索できる機能があります。
検索する際は、まず希望エリアと賃料、広さなどの基本条件を入力し、その後「こだわり条件」や「詳細条件」から「SOHO相談」「事務所可」といった項目にチェックを入れて探してみましょう。
ただし、サイトによって表記が異なる場合があるため、「事業用」「店舗・事務所」などのカテゴリーも確認してみることをおすすめします。
不動産会社に直接相談する
ポータルサイトで見つからない場合は、不動産会社に直接相談するのも有効な手段です。
特に、事業用物件を専門に扱っている不動産会社や、地域の情報に詳しい地元の不動産会社は、サイトに掲載されていない未公開物件の情報を持っている可能性があります。
相談に行く際は、希望条件に加えて、具体的な事業内容、来客の有無や頻度、従業員の人数などをまとめた資料を持参すると話がスムーズに進みます。
事業内容を正確に伝えることで、不動産会社も大家さんに対して交渉しやすくなり、より希望に近い物件を紹介してもらえる可能性が高まります。
「SOHO可」「事務所可」物件の注意点
ポータルサイトなどで「SOHO可」や「事務所可」と記載されていても、どんな業種でも無条件に許可されるわけではありません。
大家さんや管理会社は、建物の他の入居者とのトラブルを避けるため、事業内容を重視する傾向があります。
特に、不特定多数の人の出入りが多い業種(学習塾、サロン、整体院など)や、大きな音や振動、臭いが発生する可能性のある業種は、断られるケースが多いです。
そのため、問い合わせの段階で自身の事業内容が受け入れ可能かどうかを必ず確認するようにしましょう。
契約前に必ず確認すべき重要ポイント

希望の物件が見つかったら、申し込みや契約に進む前に、必ず確認しておかなければならない重要なポイントがいくつかあります。
これらの確認を怠ると、契約後に「思っていた使い方ができない」といったトラブルにつながる可能性があります。後悔しないためにも、以下の点は必ず明確にしておきましょう。
契約形態は「住居契約」か「事業用契約」か
SOHO・事務所利用可物件の契約形態には、大きく分けて「住居契約」と「事業用契約」の2種類があります。
どちらの契約になるかによって、初期費用や毎月の賃料にかかる消費税の有無、適用される法律などが大きく異なります。
一般的に、SOHO利用の場合は住居契約、事務所利用の場合は事業用契約となることが多いですが、物件や大家さんの意向によって異なります。契約後のトラブルを避けるためにも、どちらの契約形態になるのかを必ず事前に確認しましょう。
それぞれの契約形態の詳しい違いについては、後ほど詳しく解説します。
看板や表札の設置は可能か
事業を行う上で、看板や表札は重要な役割を果たします。しかし、建物の外観を損なう、他の入居者の迷惑になるなどの理由から、看板や表札の設置を禁止している物件は少なくありません。
設置が可能な場合でも、サイズやデザイン、設置場所などに細かい規定が設けられていることがほとんどです。
エントランスの集合ポストやドア横の表札スペースに、社名や屋号を記載することが許可されるのか、それとも一切の掲示が認められないのか、具体的なルールを必ず確認しておきましょう。
不特定多数の人の出入りは問題ないか
SOHO利用であっても、打ち合わせなどで来客がある場合は、人の出入りについて確認しておく必要があります。
特に、オートロック付きのマンションの場合、来客のたびにエントランスまで迎えに行く必要があるのか、それとも室内から解錠できるのかは、日々の業務効率に大きく影響します。
また、学習塾やサロンのように、不特定多数の顧客が頻繁に出入りする業種の場合は、そもそも入居が許可されない可能性が高いです。
自身の事業内容を正直に伝え、どの程度の人の出入りまでが許容範囲なのかを具体的に確認することが重要です。
法人登記は可能か
法人として事業を行う場合、本店所在地の登記が必要になります。しかし、賃貸物件の場合、大家さんが物件の住所を法人登記に利用することを許可していないケースがあります。
理由としては、登記されることで物件が「事業用」であると公になり、税務上の問題が発生する可能性や、退去後も登記が残ってしまうリスクを懸念するためです。
法人登記を予定している場合は、契約前に必ず登記が可能かどうかを確認し、可能であればその旨を契約書に明記してもらうようにしましょう。
消費税の扱いはどうなるか
契約形態によって、賃料や共益費、礼金、更新料などに対する消費税の扱いが変わります。
住居として使用する部分と事業として使用する部分の割合に応じて、消費税が課される範囲が異なります。
一般的に、住居契約で事業利用の割合が少ない場合は非課税、事業用契約の場合は課税対象となります。
資金計画にも影響する重要なポイントですので、不動産会社にしっかりと確認し、理解した上で契約に臨みましょう。
契約形態による違いを徹底解説
前述の通り、SOHO・事務所利用可物件の契約には「住居契約」と「事業用契約」があります。この二つの契約形態は、単なる名称の違いだけでなく、法律上の扱いや費用面で大きな差があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の事業スタイルに合った契約を選ぶことが大切です。
住居契約の場合のメリット・デメリット
住居契約は、あくまで「居住」がメインであり、事業での利用は従属的なものと見なされます。
メリット
- 賃料や礼金、更新料に消費税がかからない。
- 初期費用として敷金(保証金)が事業用契約に比べて安い傾向がある。
- 借地借家法が適用されるため、借主の権利が強く保護される。
デメリット
- 事業利用できるスペースの割合に制限がある場合が多い(例:床面積の50%未満など)。
- 看板の設置や法人登記が認められない可能性が高い。
- 経費として計上できる範囲が限られる。
事業用契約の場合のメリット・デメリット
事業用契約は、事業を行うことを主目的とした契約です。
メリット
- 看板の設置や法人登記が認められやすい。
- 不特定多数の人の出入りもある程度許容される場合がある。
- 賃料や初期費用などを全額経費として計上できる。
デメリット
- 賃料や礼金、更新料に消費税が課される。
- 初期費用として高額な保証金(賃料の6ヶ月~10ヶ月分など)が必要になることが多い。
- 借地借家法の一部の保護が受けられない場合がある。
- 原状回復義務の範囲が住居契約よりも厳しくなる傾向がある。
どちらを選ぶべきかの判断基準
どちらの契約形態を選ぶべきかは、事業内容や規模によって異なります。
来客がほとんどなく、自宅でのデスクワークが中心のフリーランスの方であれば、費用を抑えられる「住居契約」が適しているでしょう。
一方、法人として登記が必要な方、従業員を雇用する予定がある方、来客が多い業種の方などは、事業活動の自由度が高い「事業用契約」を選ぶ必要があります。
自身の事業計画と照らし合わせ、不動産会社とも相談しながら慎重に判断しましょう。
SOHO・事務所利用可物件を契約する際の注意点
物件探しから契約形態の確認まで、多くのステップを経て、いよいよ契約となります。最後の段階で失敗しないために、契約時に特に注意すべき点を3つご紹介します。
大家さんや管理会社との良好な関係を築き、安心して事業を続けるためにも、必ず押さえておきましょう。
大家さんや管理会社へ利用目的を正確に伝える
最も重要なことは、利用目的を偽りなく正確に伝えることです。
「在宅ワークのようなものだから大丈夫だろう」と自己判断し、無断で事業を始めると、契約違反として退去を求められる可能性があります。
どのような事業を、どのくらいの規模で、どの程度の頻度で来客があるのかなど、具体的な情報を正直に伝えましょう。
誠実な対応を心がけることで、大家さんや管理会社からの信頼を得られ、入居後のトラブル防止にもつながります。
事業内容を具体的に説明する
「IT関係の仕事です」といった曖昧な説明ではなく、誰が聞いても理解できるように、事業内容を具体的に説明することが大切です。
事業内容を説明する簡単な資料(ウェブサイトのコピーや事業計画書など)を用意しておくと、より説得力が増し、スムーズに理解を得られます。
他の入居者への影響が少ない事業であることをアピールできれば、大家さんも安心して許可を出しやすくなります。
契約書の特約事項をよく確認する
契約書には、通常の賃貸借契約の内容に加えて、事業利用に関する特約事項が記載されている場合があります。
例えば、「看板設置不可」「不特定多数の出入りを禁ずる」「法人登記不可」といった内容です。
口頭で確認した内容であっても、契約書に記載されていなければ法的な効力を持ちません。
契約書の内容を隅々まで確認し、事前に聞いていた話と違う点や、不明な点があれば、署名・捺印する前に必ず質問して解消しておきましょう。
まとめ
SOHO・事務所利用可の賃貸物件探しは、一般的な住居探しとは異なる視点と注意が必要です。物件数が限られているだけでなく、契約形態や利用条件など、確認すべき項目が多岐にわたります。
重要なのは、自身の事業内容を正確に把握し、それを不動産会社や大家さんに誠実に伝えることです。そして、契約前には、契約形態、看板設置、法人登記の可否といった重要ポイントを一つひとつクリアにしていくことが、後のトラブルを未然に防ぎます。
この記事で解説したポイントを参考に、ご自身の事業に最適なワークスペースを見つけ、ビジネスを成功させてください。